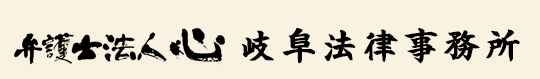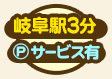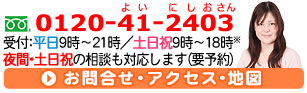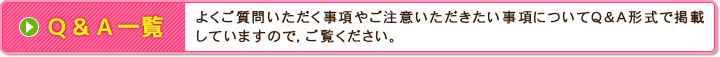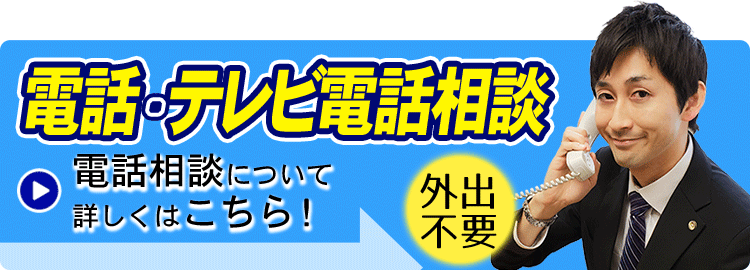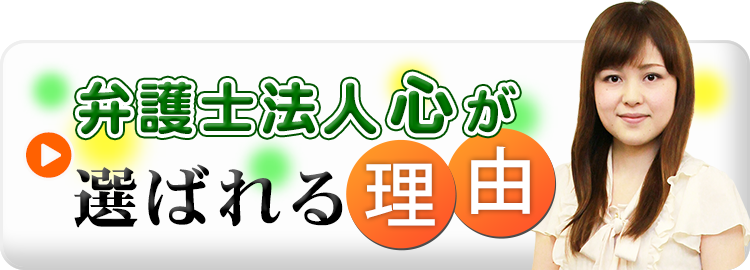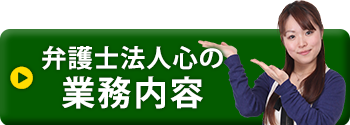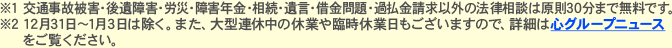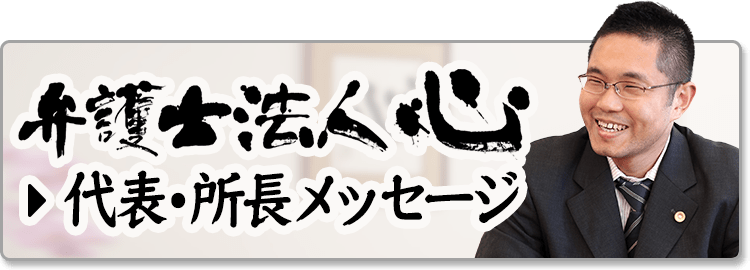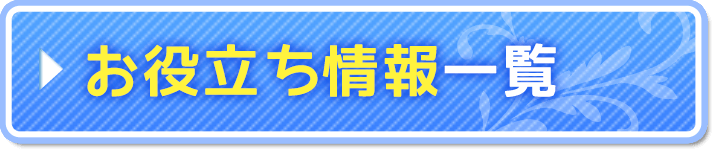寄与分がある場合の遺産分割
1 寄与分が認められる場合
相続人に寄与分が認められる場合、その相続人の遺産分割における相続分が増加します。
どのような場合に寄与分が認められるかというと、被相続人の家事や家業に従事した場合、療養看護をした場合、金銭等を出資したり、財産の維持や管理をしたりした場合に寄与分が認められる可能性があります。
ただし、法律上も「特別の寄与」をした場合にのみ寄与分が認められるため、親族として通常の貢献にとどまるものであったり、貢献に対する報酬を受けたりした場合には、寄与分は認められません。
2 協議における寄与分の扱い
相続人間で遺産分割協議をする場合に、「特別の寄与」と法律上いえるかどうかに関わらず、相続人全員が、その貢献を認めたうえで、その相続人が他の相続人よりも多くの財産を相続することに合意することは問題ありません。
たとえば、亡くなった方が施設に入所しており、特定の相続人が遠方から施設に通って面倒を看ていた場合、基本的には、施設の入所中の療養看護には寄与分は認められませんが、他の相続人もその事実上の貢献を認めたうえで、面倒を看ていた相続人に多くの財産を相続させることに応じることは差支えありません。
3 法律上の寄与分の扱い
相続人に寄与分が認められる場合の法律上の扱いを、例を挙げて説明します。
たとえば、相続人が妻と長男、長女の3人のケースで、相続財産が5000万円だとします。
寄与分が認められない法定相続である場合には、妻が2分の1の2500万円、子ども2人がそれぞれ1250万円ずつの相続となります。
他方、長男に1000万円の寄与分が認められる場合には、まず、相続財産の5000万円から寄与分の1000万円を控除した4000万円を法定相続で分配します。
法定相続で分配すると、妻には2000万円、子どもそれぞれは1000万円の相続分がありますが、長男には、認められた寄与分の1000万円を加えた2000万円が相続分となります。
この相続分は具体的相続分というものですが、これによって遺産分割の内容がすべて決まるわけではなく、たとえば、不動産が遺産に含まれている場合などには、遺産をどのように分割するかの内容を、具体的相続分をもとに決めることになります。
寄与分の主張がある場合には、裁判手続きにおいて「寄与分を定める処分調停」という手続きをとる必要がありますので、ご注意ください。
4 相続人以外に寄与分が認められる制度が創設
これまで、寄与分はあくまでも相続人間の公平性のための制度とされ、相続人にしか寄与分の主張が認められませんでした。
そのため、亡くなった方の療養看護を一生懸命務めてきたのが、相続人である長男ではなく、長男の妻であった場合、長男の妻は相続人ではないため、寄与分の主張は認められず、長男の妻の貢献を長男の貢献であるとみなして、長男の相続分を増やすことでしか調整ができませんでした。
しかし、このような方法は、実際に貢献してきたのは長男ではなく長男の妻であることや、長男が仮に親よりも先に亡くなってしまった場合は、長男の妻にそれまでの貢献分を考慮して財産を渡すことはできなくなってしまうなど、問題点がありました。
そこで、法改正により、相続人以外の親族にも「特別寄与料」を請求することができる制度が創設されました。
特別寄与料の請求は、遺産分割とは異なる手続であり、特別寄与者から相続人に対して請求することで決めることになりますが、遺産分割が一度成立してしまった後だと、誰が特別寄与料を支払うかということでもめることが想定されますので、できれば、遺産分割のタイミングで一緒に解決することができるようお話し合いを進められた方がよいかと思います。