大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
詐欺
詐欺事件発生からの流れ
送検・勾留まで
逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。
依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。
事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,騙していない物的証拠や証言を提示し,早期釈放に向けての弁護活動を行います。
詐欺で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。
警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。
決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。
留置中,家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが,弁護士はであれば,ご依頼者様との面会が可能です。
制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
詐欺で送検・勾留されないようにするために,被害者への謝罪,示談金の支払いをし,嘆願書の獲得などを行います。
振り込め詐欺など,組織的で,被害者の数・被害額も多い場合,すべての被害者と示談を成立させるのは難しく,また仮にできたとしても事件の性質上,通常は起訴されてしまいます。
その場合は,起訴された場合に備えた活動も同時に並行して行います。
無銭飲食などで,余罪もなく,被害金額も少額の場合,不起訴となる可能性は高くなります。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。
勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。
組織的で余罪も多い振り込め詐欺等の場合,20日間の勾留期間が終わると,別の被害者の事件として再逮捕が繰り返され,長期間の勾留がなされる場合があります。
不起訴獲得に向けての活動と同時に,再逮捕されない,長期間勾留されないための弁護活動も行います。
黙秘権の行使もただ沈黙しているだけでは勾留の長期化を招くばかりで,ご依頼者様自身の利益になりません。
早期釈放,執行猶予獲得に向けての弁護方針において,黙秘権行使がいつどのタイミングで必要なのかも,ご依頼者様と相談の上検討します。
無銭飲食,無賃乗車など,組織的でなく比較的軽微な詐欺の場合,被害者との示談,嘆願書の獲得により,早期釈放を目指した弁護活動を行います。
また証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に訴え,弁護士を通じての身元引受人確保,保釈保証金の準備も進め,保釈請求を行なっていきます。
起訴から裁判まで
起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。
裁判が行われるまで引続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。
請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
振り込め詐欺など組織的な詐欺の場合,関係者と共謀して証拠隠滅や逃亡をする恐れがあると判断されることが多く,保釈の獲得は極めて困難です。
そのため,より一層の工夫が必要となります。
なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。
保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。
起訴後は執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。
振り込め詐欺など組織的な詐欺行為の場合,実際関与していた人は,実刑判決が出る可能性が非常に高いです。
ただし必ずしも実刑になるわけではありません。
被害者への謝罪と賠償,本人の反省,更生の意思を明確化し,裁判官に訴える弁護活動によって,執行猶予付き判決を獲得できることもあります。
刑事免責
1 刑事免責とは

刑事訴訟法146条で保障される証言拒絶権をはく奪して供述させる一方で,その証人自身の刑事事件では,その証言及び証言から派生して得られた証拠の使用を禁止する制度をいいます。
刑事訴訟法改正により新たに導入された制度であり,平成30年6月1日から施行されます。
2 想定される事案
組織犯罪が刑事免責適用の典型的事案といわれています。
すなわち,上位者の処罰を実現するために下位者を免責して証人尋問での証言を強制するために使用されることが考えられています。
3 要件
検察官が,①「当該事項についての証言の重要性,関係する犯罪の軽重及び情状その他の事情を考慮」し,②「必要と認めるとき」に,裁判所に請求することができます(法157条の2,157条の3)。
いわゆる「取引」ではなく,被疑者・被告人の同意は不要であること,また,裁判官に刑事免責するかの裁量がなく,検察官による請求があれば原則として免責しなければならないことに特徴があります。
4 効果
裁判所が刑事免責することで,①証人は,刑事訴追を受けたり,有罪判決をうけるおそれのある事項に関する証言であっても強制されることになります。
その結果,証言拒否罪や偽証罪が適用されるようになります。
また,実効性確保の観点から,宣誓拒絶罪と証言拒絶罪について大幅な厳罰化が図られました。
②他方で,義務付けられた供述や,これに基づいて得られた証拠は,その証人の刑事事件において不利益な証拠とすることはできなくなります。
具体的な供述をすればするほど免責の範囲が広がりうることになります。
もっとも,他の証拠に基づいて刑事訴追されて有罪判決を受ける可能性はあり,完全に罪に問われなくなるというものでないことに注意が必要です。
5 刑事弁護への影響
刑事免責制度の施行前であり,今後の運用の中で刑事弁護活動にいかなる影響が生じるか明らかになるため,注視していく必要があります。
もっとも,現時点でも,被告人の供述内容を知るための制度利用される可能性が懸念されています。
すなわち,捜査機関が,被告人黙秘のとき,共犯者の証人として呼び,刑事免責請求して,供述を強制させ,その供述内容(弁護方針等)を知ることが可能となったのです。
6 お気軽にご相談ください
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,刑事事件を数多く取り扱うとともに,司法取引や刑事免責制度など新しい法制度の研修など日々研鑽に努めております。
岐阜でお困りの場合には,お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
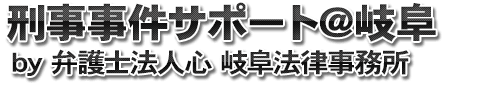

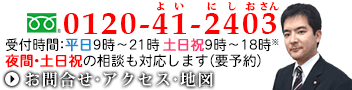
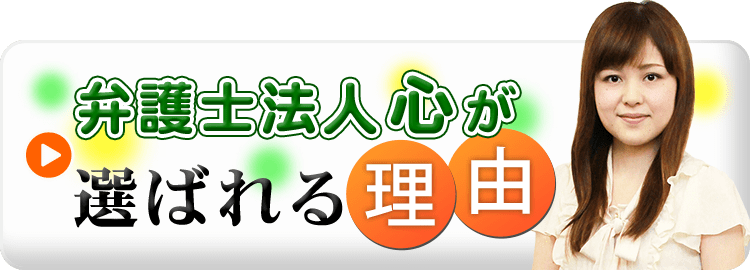




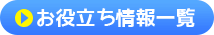

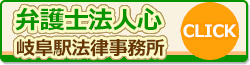




詐欺は主に企業をターゲットにした取り込み詐欺や,主に個人をターゲットにした寸借詐欺,振り込め詐欺など多くのパターンがあります。
無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。